こんにちは むうさんです^^
写真撮影で悩むことの一つに、自分の撮影した写真の質は、何をやったら上がるのか?
ということです。
”質 ”という言葉が広すぎますが、
その一つとして、写真を見た時の印象をどうしたいのか?
自分が伝えたい印象になる写真が撮れているのか?
ということがあります。
残念ながら、
写真から受ける印象、与える印象について、私はわかっていないので、行き当たりばったりになっています。
そんな私が、この写真ではこんな印象を与えますよ?
ということを教えてくれる本に出会いました。
『日常風景写真術 栗栖誠紀著』

おすすめ写真本のブックレビューです。
筆者からのメッセージ
私がこの本の背表紙をみて、手に取ったのは、”日常”というワードがあったから。
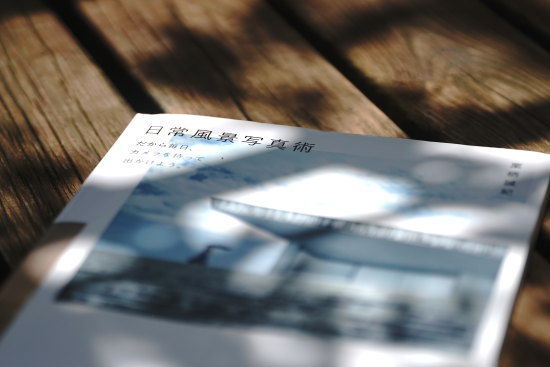
大げさな写真や、加工前提の絶景写真術のようなものは、今の自分は、興味はあっても醸成中?な感じで、その手前にいるから。
手に取ってみると、1枚の写真がどんな印象を与えるのか?
普段、自分がみているような日常風景をもとに説明してくれていました。
『日常風景写真術』 はじめにを読むと
「はじめに」から抜粋すると、
本書では筆者が今まであちこちで写真を撮ってきて感じたことや、どのようなイメージを持って一枚の写真にしたかなどのエピソードを加えつつ、基本的な撮影テクニックや表現について、また最終的にどのように仕上げたのかまで解説する。
イメージがあってもなかなかうまく写真に表現できなかったり、見た目ですごく美しいと思っていたのに、写真にしてみたらそうでもなかった……、なんていうことが少なくなるように本書を役立てていただきたい。
とあり、
自分のイメージを、また、どんなイメージを抱きながら撮影しているかを教えれくれる本です。

日常写真の撮影術 中身は?
この本の目次は、下の通りですが、この本の大部分の7割のページはCHAPTER2と3に割かれています。
CHAPTER1 カメラを知る・写真を撮る
CHAPTER2 四角形に切り取る話 フレーミング&アングル
CHAPTER3 表現の話
CHAPTER4 デジタルカメラの基礎知識
CHAPTER5 写真の仕上げ・発表
そして、私が参考になったのも、そのCHAPTER2,3と5です。
そのCHPTER2の最初に、筆者の凝縮された写真への考え方が書かれています。
肉眼で見ている風景や被写体の一部を切り取って写真にしなければならないので、「フレーミング(構図)」と「アングル(カメラの高さ)」はとても重要なのだ、この2つは写真の中の「主食」と言えるかもしれない。
第1章で解説した絞りとシャッタースピードは「おかず」みたいなもので、3章で解説する光や露出もある意味「おかず」と言えるだろう。なぜなら、まず写真は「何を撮っているのか」「どんな風に切り取ったか」がとても大切だと筆者は考えるからだ。これがいわるゆ「画づくり」である。
「フレーミング(構図)」と「アングル(カメラの高さ)」が写真撮影の「主食」と言っているのです。
私の中に、この考え方がスーッと入ってきました。

写真を撮りはじめて、絞りをどうしよう、手ブレをしないようにシャッタースピードを注意しようという前に、フレーミングとアングルを第一に考えて、その後に筆者の言う「おかず」である絞りやシャッタースピードがあり、光や露出も「おかず」なんだと言っています。
自分の写真撮影するときの優先順位が明確になりました。
まずは、この筆者の考え方に合わせようと、フレーミングを決める前に、滝で水の流れを表現するなら1/4のシャッタースピードだな、とか、花を撮るなら絞りは開放気味でぼかそうと考える前に、まずはフレーミングとアングルを決める。
まずは、やってみようと思います。
筆者からのアドバイス
一つ目のアドバイスは、『引きと寄りの写真2点で1つの世界をつくってみる』です。
チャレンジしました。
まずは引きの写真です。
「誰もいないベンチを意識して撮影した。静寂感を演出している。」という筆者の真似です。

それに対して、寄りの写真では、「使い古された様子が捉えられ、人の気配を思わせる仕上がりになった」と筆者が言う感じで撮ってみました。

引きの写真と寄りの写真を、同じ被写体に対して撮ると、伝えられるイメージが変わることがわかります。
たくさんのアドバイスをくれます。
・縦位置と横位置でで撮影しておく。
・高い所と低い所からのアングルで撮影する。
アングルの説明の中では、参考になる写真がないのですが。
アイポイントでのアングルでは、
「団地の中にある小さな公園。砂場に枯れ葉がたくさん落ちていて、人の気配がない雰囲気に寂しさを感じる。背景がやや雑然とした印象だ」
高い位置からのアングルでは、
「公園の横にある団地の非常階段から撮影。上から見ることで画面が整理された。枯れ葉の絨毯と奥からの光が景観全体をノスタルジックな印象にしている」
とあり、さまざまなアングルから撮影したときに、どのような印象になるかを教えてくれます。自分でもさまざまなアングルで撮影することで実感しきたいと、撮影意欲が湧いてくるアドバイスです。
そして、ページの途中途中には、筆者のさまざまな作品が載っていて、写真もとても楽しめます。

他にも、モデルを撮影する場合は、モデル同じ位置に立ってもらい、右寄り、左寄り、中央と3つのバリエーションで撮影すると、背景が変わって意外と印象が違うことに気づける。
とか、撮影するときに、そういうふうにバリエーションをつくるのか?確かに印象が変わる!と実感させてくれます。
日常風景写真術 CHAPTER3 表現の話
自分なりの表現ができた写真を撮影したい!と思っていて、このCHAPTER3は、とても参考になりました。
筆者の言葉では、「3章で解説する光や露出もある意味「おかず」」ということだったが、その「おかず」が、「あなたらしさ」をつくるとても大切なものだと教えてくれます。
第3章の冒頭から抜粋すると、
第2章の冒頭でフレーミングとアングルは「主食」で、それ以外が「おかず」ということを伝えた。「おかず」というと語弊があるように感じる読者もいると思うが、しかしこの「おかず」がいわゆる撮影者の表現にあたる部分だ。きれいなものをきれいに撮ることはもちろん大切なことだが、同じ被写体を撮影しても「あなたらしい」と人から言ってもらえるようになると、そこには人なりの表現が存在することになる。
~途中省略~
撮影者は、なぜその被写体に対して魅力を感じたのか、どこに惹かれたのかをよく考えることで自分なりの表現が可能になる。言い換えれば、読者が被写体に対して持っている思い出やエピソードなどがあることで、読者しか撮影することのできない写真表現につながっていくことになる。
光の見方、写真の見方を教えてくれます。くわしくは、是非、読んでみてください。
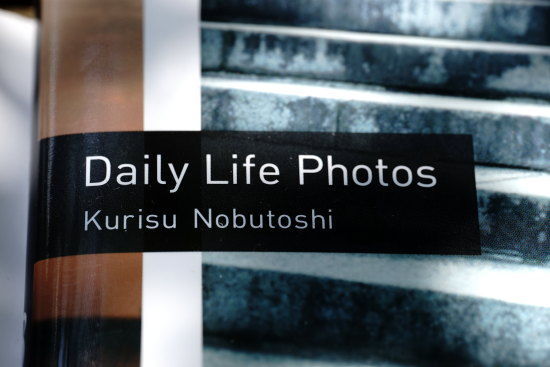
その中でも、筆者が何度か繰り返して言っていたのが、「ざわと空間を多く作って撮影すること」をトライしていってほしい。ということ。
そうすることで「メインの被写体と同じように周りの空間を見ることで、写真表現の幅が広がるはずだ。」と言ってくれています。
この章では撮影者の表現したいことを実現するカメラの機能や、現場で少し工夫することでできる表現を紹介する。これを読んで実践してもらうだけでんも、かなりの気づきがあるはずだ。読者にはこの気づきをきっかけに繰り返したくさんの写真を撮っていく中で、自分なりの表現を見つけていってほしい。技術的なことや工夫を試すことで、何か1つでも「自分なりの表現」を見つけることができたら、写真は劇的に変わるはずだ。
このように、CHAPTER3:表現の話では、「自分なりの表現」を見つけるために試すためのヒントが詰まっています。
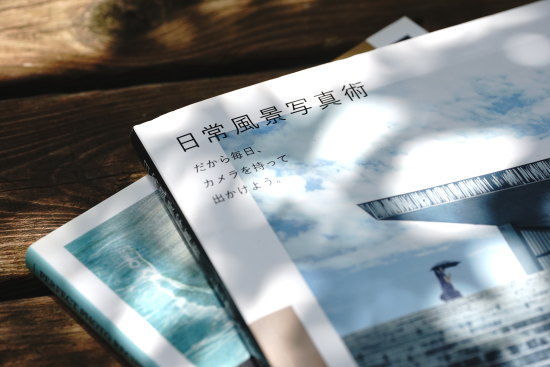
写真撮影をしていて、「人にどう伝わるか知りたいという基本的なことから、人に伝わる写真を撮りたい、自分なりの表現をしてみたい。」ときれいに写っている写真の先にあるものを目指したいと思っています。
きれいな写真の先にある「自分らしさ」ということまで、いっぱいのものが詰まった『日常風景写真術 栗栖誠紀著』です。是非チェックしてみてください。