こんにちは むうさんです^^
秋が過ぎて、冬になりました。
ミニ盆栽も、葉を落としたり、枯らすことによって、冬を表現してくれています。
クヌギは、葉を落とさない樹木で、トウカエデ、ケヤキ、イチョウ、コナラは、落葉します。

そんな樹木の違いを含め、冬のミニ盆栽をご紹介します。
冬のクヌギ
クヌギは、落葉樹に分類されますが、葉を落としません。
風が吹くなどして、外的な影響で葉を落とすことはあっても、自ら葉を落とさないのです。
普通の落葉樹は、離層をつくり、自らの重さに耐えられなくなって葉を落とします。

室内の出窓という、ヌクヌクして風も吹かない場所のため、葉を落とさないで残っています。ただ、換気のために窓を開けたときの風で、落ちているクヌギの葉っぱもあります。

葉っぱが残っていると次の葉がでないのでは?と心配になります。
ですが、葉っぱが落ちなくても、枯れた葉っぱの根元に芽がついているはずなのですが……。見当たりません。

クヌギは昨年で3年目のものありましたが、春に、トウカエデやイチョウ、コナラ、ケヤキが芽吹いても、ずっと葉を出さないままでした。そして、諦めた頃に葉を出したのです。
▼梅雨の時期に芽生えたクヌギ
復活したクヌギの中で、一つだけは元気で緑色の茎で、芽らしきものがあるので今春の芽吹きに期待!です。

クヌギの中でも大きな鉢で育てているクヌギだけは、順調に30cmの高さまで育っています。

そして、過去の経験からポッドが大きいほど、芽を出し直す率が高いことがわかっています。
▼実験!ポッドのサイズ大中小と芽が出る率との関係
実際に、30cmのクヌギには春になると葉っぱがでてくる冬芽が見られます。期待!したいです。

昨年、近くにあったクヌギが切られてしまい、ドングリを簡単に拾えなくなりました。
残ったクヌギたちが、今春、発芽してくれるといいのですが。
冬のコナラ
コナラも、クヌギと同じブナ科コナラ属で親戚なので、落葉しにくい樹木です。
実際には、落葉どころか緑色の葉っぱのままのコナラまでいます。

上の写真の通り、1つのコナラだけグリーンなので、とっても目立ちます。

今年が異常な暖冬のため、暖かくて黄葉することも、葉を落とす必要も感じていないのかもしれません。
落葉とは、樹木が冬に身体の中の水が凍って細胞死しないようにする、寒さを凌ぐ進化の結果なので、寒くないのであれば、落葉する必要がないのです。下に書籍の説明を抜粋します。
秋から冬は葉を失ったために、葉からの蒸散が起こりません。葉がないことは根からの水の吸い上げに影響します。葉からの引き上げる力が無くなるのですから、水を体内に取り込みにくくなります。そのため体内水分量が下がるので、樹皮下にある細胞液が濃くなるのです、これで細胞内が不凍液化し、低温になっても細胞死することが少なくなります。
※大人の樹木学 石井誠治著より抜粋
『大人の樹木学 石井誠治著』は、樹木について大人が読んで面白いネタが豊富な本でオススメです。是非、チェックしてみてください。
▼大人の樹木学 石井誠治著
とはいえ、落葉しているコナラもあり、心配なので冬芽があるか見てみました。

観察してみると、

他のコナラの枝の先端にも冬芽?がありそうです。

クヌギもコナラも、今春の芽吹きを期待です!
コナラの樹木としての戦略
コナラの生き残り戦略
コナラのミニ盆栽を育てていますが、コナラってどんな樹木で、どんな生き方をしているのか知りたくなりました。
ここでは、コナラの生き方について、『イタヤカエデはなぜ自ら幹を枯らすのか 渡辺一夫著』を参考に、ご紹介したいと思います。
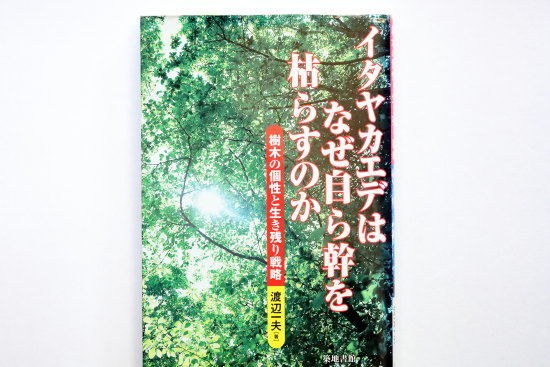
コナラは、炭などに使っていた昭和30年代までは、人に役立つ樹木でした。ですから、人の手によって勢力を拡大してきました。しかし、炭などを使わなくなってからは、誰もコナラを切って使うこともなく、現在は老いたコナラたちが、ナラ枯れなどで被害を受けて、少しずつ衰退しています。
「コナラの寿命はかなり長いので、今あるコナラがすぐに倒れることはないだろうが、コナラの若い世代が増える可能性は少ない」と書かれています。
人に助けられ、里山で帝国を築いてきたコナラですが、崩壊の時期は迫ってきているようです。
おすすめの本 樹木の個性と生き残り戦略:3部作+1
渡辺一夫さんの、樹木の個性と生き残り戦略の3部作は、樹木の生き方、生き残るためにどうしているのか?海岸沿いに生き残る樹木、枝を自ら落とす樹木、種のままずっと耐える樹木、暗いところでも生きられるが生長が遅い樹木、など、おもしろい話が盛りだくさんです。
私は、樹木の生存戦略を知りたくて、本を探しまくったのですが、樹木の本がなかなかなく、ようやく見つけた超おすすめの3部作の本です。是非、チェックしてみてください。
▼イタヤカエデはなぜ自ら幹を枯らすのか 渡辺一夫著
▼アセビは羊を中毒死させる 渡辺一夫著
▼アジサイはなぜ葉にアルミ毒をためるのか
+1冊は同じく渡辺一夫さんの『街路樹を楽しむ15の謎 渡辺一夫著』です。
イチョウをはじめ、ケヤキ、ソメイヨシノ、ハナミズキ、コブシ、ポプラ、プラタナス、トチノキなど、15種類の街路樹について、その生き方などを紹介しています。是非チェックしてみて下さい。
▼街路樹を楽しむ15の謎 渡辺一夫著