こんにちは むうさんです^^
143ページ、ぎっしりと富士フイルムのカメラのの画質について書かれた、富士フイルムの公式?本です。
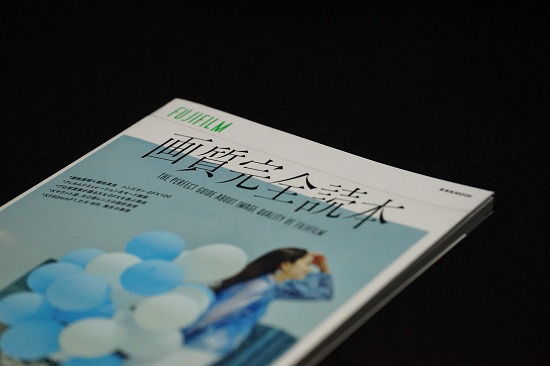
この本は、富士フイルムの画質の本のため、写真が豊富に載っています。
その写真の作例を見ながら、フィルムシミュレーションなどの画質についての説明を読むと、腑に落ちることが多いです。写真があってのこの読本かなと思います。ご興味があれば、是非手にとってご覧ください。
画質完全読本スタート
FUJIFILMのセンササイズ
最初に、なぜAPS-Cとラージフォーマットの2つのセンササイズを選んだのかが、書かれています。
コンパクトであり高画質。
画質、機動力、価格。それらのバランスを考えると、APS-C妥当確信し。
とあります。
現在カメラは、フルサイズがもてはやされています。
一方で、スマホが普及し、差別化などの理由でカメラが高価格になってしまい、カメラは一部の人が買う物になる中で、APS-Cのセンササイズを選択するということは。
それは、富士フイルムが画質に自信があるからこそ、価格とコンパクトなサイズでの機動力で勝負できるのだと思います。
※センササイズは、フルサイズの方がAPS-Cよりも大きく、一般には、フルサイズの方が高画質を考えられています。
FUJIFILM 画質完全読本の3つの軸
一方で、画質についてのとことんのこだわりは、フルサイズを超えた、より大きなセンササイズのラージフォーマットのカメラに表れています。こだわるなら徹底的にと、フィルムメーカーとしてのフジの画質に対する執念を感じます。
『FUJIFILM 画質完全読本』では、画質について下の3つを軸にしています。
② フィルムシミュレーションをはじめとした、画像処理での画質
③ レンズの性能
1億2百万画素のラージフォーマット
1億2百万画素のラージフォーマットカメラ『GFX100』の圧倒的な描写力を写真家さんが、ポートレートで魅せてくれます。
写真家は、ふたりのお子さんを撮影した「ハルとミナ」で有名な澤田秀明さんです。
画質完全読本から抜粋すると、
「フィルム時代からXシリーズに至るまで「記憶色」という呼び方」
「「記憶色」は人が目にして気持ちが動いたときの色」
「人物を撮ると、立体感や奥行き感がとても印象的に出ている」
澤田さんは、ポートレートでは、フィルムシミュレーションでASTIAを使ったとのことです。
「人肌の表現が好きでした。撮ったものがそのまま良いと思えるデジタルは、僕の中では初めてでした。」
と感想を述べています。
富士のフィルムシミュレーションとGFX100の組合せは素晴らしいのでしょう。
ポートレート写真を見ると、もちろん凄いと思えるのですが、正直、凄すぎてわからないというのが本音です。写真家の方が語ることで説得力が増します。
そして、富士フイルムのカメラと言えば、『フィルムシミュレーション』。そのフィルムシミュレーションは、もちろん詳しく解説されています。
フィルムシミュレーション
クラシックネガ
フィルムシミュレーション、最初にクラシックネガが登場します。
フィルムライクに撮影したいという人が多く、一番人気のあるフィルムシミュレーションです。
そのような人気のクラシックネガの画質設計の考え方が、作例とともに詳しく書かれています。
『マゼンタ気味のシャドウ、ハイライトに緑が乗る。』
など、作例を見ながらなので、どういう写真だとわかるのか、どういう写真の時にクラシックネガを使うと特徴が出るのかが伝わってきます。
自分が撮りたい写真のイメージと、フィルムシミュレーションが結び付けられるようになってくるので、富士フイルムのカメラでクラシックネガを使う時に役立つでしょうし、作例をみていても、その色合いに惹き込まれて行く感じがいいです。
クラシックネガが3ページ、エテルナブリーチバイパスは2ページ、PROVIA/スタンダードは2ページ。予想通り、クラシックネガがフィルムシミュレーションの中で多く占めています。
PROVIA
PROVIAについても、熱く語られています。
「富士フイルムがフィルム製造の過程で醸成してきた「記憶色」を採り入れており、青空や海は青く、肌色は血色よく、緑はイキイキとした鮮やかな緑になる」
と、絶品の自信を持って、PROVIAの色設計を書いています。
「過度に演出された発色ということではなく、忠実であるものの、そこに絶妙な味付けをすることで美しいと目が捉えた記憶に近づけている。」
富士フイルムがフィルム時代から追求してきた、 人の記憶にある色、撮影した時の色への想いに対して、絶対的な自信を持っているのがうかがえます。
さらに、それをデジタルカメラで、再現する技術力を誇っています。
その他のフィルムシミュレーション
Velvia(ビビット)、ASTIA(ソフト)と続きます。Velviaでは色鮮やかに再現しながら、色が濃すぎてディテール(細かい部分)が失われることを抑えているようです。新機能である「カラークロームエフェクト」を使うことで、さらに鮮やかさとディテール再現を両立できるようです。
この「カラークロームエフェクト」は使ってみたいなぁと思わされます。
ASTIAでは「肌再現と鮮やかさの同居」を実現と、ソフトなだけではなく、鮮やかさもあわせ持ったフィルムシミュレーションです。
クラシッククローム、PRO Neg. Hi、PRO Neg. Std、ETERNAと、カラー系のフィルムシミュレーションの詳しい説明書が続きます。
フィルムシミュレーションの説明の最後に、カラー系のフィルムシミュレーションを、青、赤、緑、黃、人の肌のそれぞれの色が主の写真の作例で、比較しています。
空を撮るならこれ、人を撮るならこのフィルムシミュレーションとこの作例を見ているだけで、イメージが膨らんできます。
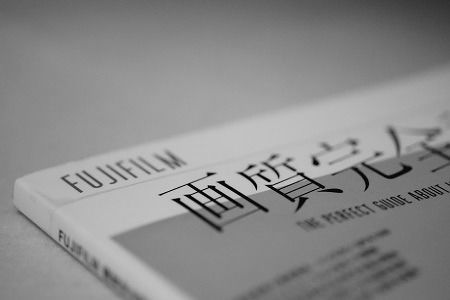
画質設定
その後には、
「カラークロームエフェクト」「カラークロームブルー」「グレインエフェクト」「ダイナミックレンジ」「トーンカーブ」「カラー」「シャープネス」「明瞭度」「ノイズリダクション」「点像復元処理」「ホワイトバランス」「超時間ノイズ低減」「ピクセルmapping」「色空間」「WBシフト」「スムーススキン・エフェクト(GFXのみ)」
と、これでもかと画質設定について書かれています。
フィルムシミュレーションの各モードは、カラーやトーンの設定をどんなに調整しても画像的に破綻しないようになっているようで、色としては富士の考える中で、成立している範囲なので安心して、カラーなどを調整できます。
また、RAWで撮影すれば、カメラの内でも現像できますし、「FUJIFILM X RAW STUDIO」を使って パソコンでもでき、操作の説明が書いてあります。
実際に、フィルムシミュレーションの撮り比べをしてみました。比較記事<1>では、18種類のフィルムシミュレーションを搭載している3つのカメラ、X-T4、X-S10、X-T30Ⅱについてスペックなどを紹介して、フィルムシミュレーションの比較写真も紹介しました。是非、ご覧ください。
マニアックな画質の話
開発者そしてモノクロ
フィルムシミュレーションや、センサー、レンズ、の開発者、デザイナーのそれぞれの話のページあり、ネイチャーフォト、ポートレート、ムービー(動画)、それぞれのフォトグラファーの作例と話あり。ムービーでのフィルムシミュレーションや、手ブレ補正、ハイスピード撮影の活用術も紹介されています。
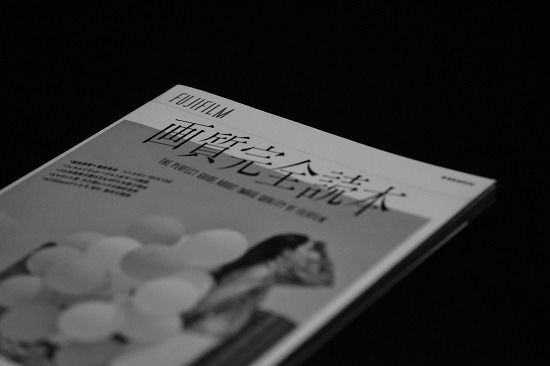
その後に、モノクロについても、しっかりと語られていて。
MONOQLOのフィルムシミュレーション「ACROSS」、「モノクロ」のそれぞれ4つのフィルターの効果が、SNAP、SKIN(人の肌)で比較され、
俳優で写真家顔負けの腕を持つ佐野史郎さんが、モノクロ写真について語ります。
画質のまつわる8つのトリビィア
「画質のまつわる8つのトリビィア 」では、
「画質の決め手は『解像感』だけじゃない」
と、読む、画質に対する発想が広がるようなこだわりの話もあり、懐かしのフィルムの話、フィルムシミュレーション列伝など、マニアックな要求にも応えた内容です。
マニアックな方はこの14ベージにびっしりと詰まっだ内容にそそられるかもしれません。
手元に置いて、何度も読み直し、富士のカメラを使いこなすのに、これ以上はない本です。
名物商品企画者 上野隆さん
富士フイルムの名物商品企画者の、上野隆さんのコラムが面白いです。商品企画者の裏話を教えてくれます。
画質設計者の「後処理しないとよい色にならないカメラなんてダメだ」という考え方が、フィルムシミュレーションを増やす原動力のようです。そんなにJPEG撮って出しに自信を持つ開発者によって送り出されたカメラ。欲しくなります……。
Xシリーズ、GFXのカメラとレンスの紹介。撮影時の設定について、詳しく説明があります。
フレームの外を見渡しながら、シャッターを切れる、スポーツファインダーモード、にいいなぁと感じました。
読んでも、読んでも、読み飽きない。
富士フイルムのカメラの画質について語り尽くそうとする本です。
富士フイルムのカメラを持っている方、購入を検討されている方、そして、私のように写真画質について興味のある方などに、とてもおすすめの本です。
是非、チェックしてみてください。
FUJIFILM 画質読本を読むと^^
写真を撮りたくなる
クラシックネガの写真で、公園の鉄棒の周りを緑の木々が囲んでいるものがあります。
写真の緑色は、青々したり、輝くようなグリーンではなく、その場所に馴染み、その場所に行ったことがあるかのように感じる緑色。
頭の中の記憶に触れ、写っていない何かを思い出す、そんな緑色なのです。
この色で写真を撮りたいという欲求が湧き出てきます。
この本を眺めていると、こんな色で写真撮影してみたいと、イメージが膨らみます。
いつもの自分の写真とは違う色で、もう少し青を強めに、ほんわかアンバーを入れてと、トライする。そんな楽しみも与えてくれます。
トライの仕方がわかる楽しみ
ダイナミックレンジの範囲の調整では、「DR100」ではハイライトとシャドウをわずかに軟調化。では、「DR200」と「DR400」とさらにダイナミックレンジを広げた時は、……。
富士フイルムのカメラの使い方、撮り方、設定の仕方が、読めば読むほどわかってきそうです。
また、富士フイルムのカメラを持っていなくても、撮影時や、撮影後に、どういう方向に画質を調整していくのかがわかり、自分のカメラで試す、トライの仕方を教えてくれます。
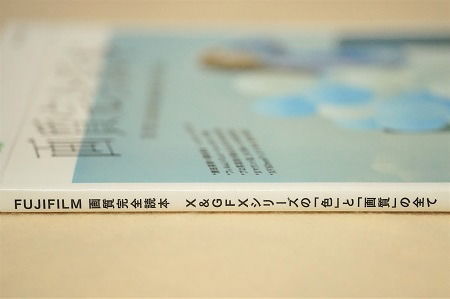
カメラを買って、自分のイメージを広げ、そのイメージを写真に落とし込みたいという方にも、この本は役立つと思います。
XFとGFレンズ、Xシリーズ、GFシリーズのカメラをカタログ。レンズのロードマップ。と情報がまとまっているのは嬉しいです。
……、……、……。
紹介しようと書けば書くほど、書き足りなさを感じてしいます。
手にとって多くの写真を見ることで富士フイルムの画質がわかるので、手に取って見てほしいと思います。チェックしてみてください。
この本は、富士フイルムの画質の本ですから、写真が豊富に載っています。
本のサイズはムックサイズで大きく。紙質はカタログに使われるようなしっかりして、写真が綺麗に印刷されていて、フィルムシミュレーションの色味も伝わってきます。そして、その写真の作例を見ながら、フィルムシミュレーションなどの画質について、写真をみると、腑に落ちることが多いです。
見ているだけでも楽しく、読むともっと楽しい『FUJIFILM 画質完全読本』。ご興味があれば、是非手にとってご覧ください。
実際に、フィルムシミュレーションの撮り比べをしてみました。比較記事<1>では、18種類のフィルムシミュレーションを搭載している3つのカメラ、X-T4、X-S10、X-T30Ⅱについてスペックなどを紹介して、フィルムシミュレーションの比較写真も紹介しました。是非、ご覧ください。